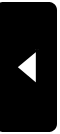5月22日(土) 劇団員が稽古に明け暮れる中、今年度の劇団静岡県史のプロジェクトの一つ、「県民参加音楽劇『マダム・バタフライ~三浦環ものがたり~』プロジェクトの支援をしてくださるアーツカウンシルしずおかのキックオフミーティングに参加しました。

アーツカウンシルしずおかとは
アーツカウンシルしずおかは、すべての県民が、様々な表現活動を通して創造的になることを目指します。
アーツカウンシルしずおかは、そのための方法を開発し、制度を整備してまいります。
特に、まちづくりや観光、国際交流、福祉、教育、産業など社会の様々な分野と、文化芸術との協働を促進し、地域資源の活用や社会課題に対応する創造的な取組を支援することにより、地域社会の創造に寄与してまいります。


というものです。
https://artscouncil-shizuoka.jp/
劇団静岡県史は、単なる演劇公演活動と違って、静岡県の歴史を舞台化するために作品に関わる勉強会を開催しますが、それでも大抵の劇団は劇団内で実施されるだけです。
しかし、その勉強会の内容があまりにも良いものだったりするので、劇団員だけでは勿体ないと感じるようになり、一般公開して地域や関心のある人たちと更に共有し、作品創りに生かします。
中には勉強会に参加して、そのまま演劇に参加する人も現れたりします。
インプットされた歴史を、演劇という形でアウトプットすることにより、更に理解が深まるどころか、当時の人たちのような体験をするのです。
それによって時代を越えた他者を知り、ある意味での多様性の理解が増えますよね。
先人たちは当時、何を感じ、考え、行動していたのか?それによって、今の足元も見えてきます。
未来が見えにくい世の中だからこそ、過去を振り返って、先人たちの知恵を借りる。
それによって、未来への予想や、指針が見えたりしてね。
そんな活動を劇団静岡県史は、創作過程で学べるのですが、今年度取り組む事業は、明治~昭和にかけてのプリマドンナ三浦環さんは世界で活躍していた人。オペラ「蝶々夫人」で蝶々さんを2,000回もの公演で演じていた人です。
因みにこの作品、イタリア語で上演されたそうですが、お話は、日本の長崎なんですね。しかもこの役、ソプラノだというのに、比較的音域は低いのだとか?
アメリカの小説を原作にオペラとして蘇った『蝶々夫人』は、日本人なのに、最初は外人が演じてたんですって。
で、そこで抜擢された、三浦環さん。
幼い頃から、日舞やお琴など、日本文化を学んできていた人ですから、重宝されると思います。
『ラスト・サムライ』で、小雪にタオルを持たせることはありません。
そのような、少々、日本人の私たちが「?」と思ってしまうような環境で生まれたエピソードなど、ちょっと面白そうですよね。
という私は、まだまだ勉強中。この創作と、勉強会を通して、脚本にのせていきます。
今年の第1回目のアーツカウンシルしずおかでは、23団体が参加して、地域密着型で様々な文化芸術活動を行っていきます。
本日のキックオフミーティングでは、単に団体紹介だけでなく、ワークショップも行われ、自分たちの活動の価値について考える時間がありました。
コーディネーター北本チームとしては、かけがわ茶エンナーレ実行委員会さん、熱海未来音楽祭さん、藤枝世代をつなぐ商店街づくり実行員会さん、そして今日は本番で参加出来なかった、特定非営利活動法人日本地域部活動文化部推進本部さん、そして我が劇団がメンバーで、共通事項や問題課題、必要性、今後の展望などを、事業が成功した時のイラストを個々の団体が描いて、ディスカッションしました。
その中の共通事項は、いつもの日常の変化や、揺さぶり、元気や刺激、そして気づく場、年齢を越えた寄合というキーワードが出てきました。
コロナ禍で、人を集めることに障害が出てきましたが、その中を連れ出して何かをやる価値、それによる新しいコミュニティや人との繋がりが生まれ、住んでいる人たちが心豊かになることを目的とする必要がありそう。
私個人は「人に迷惑をかける必要性」が、面白いキーワードだなと思いました。
そして、なんと熱海が東京の竹下通り並みに若者が集まってることを聞き、衝撃を受けたり。やはり他者と出会うと、自分との違いを知り、その中で面白い知識や方法論など知り合えて、良い刺激になりますね。
そういう意味では同じ事業支援仲間として、励まし合ったり、切磋琢磨して、更に地域を盛り上げていけるのは良いですよね。
違う意見が出たり、自分のやっていることと違ったりすると、それで人と距離をつくったり、否定されたと被害妄想を持ってシャットダウンしたりする人もいますが、多様性を認め合うことが大事だというのであれば、それを民主主義として議論し合うのは、とても大事だなと思ったりね。
他者と出会うのは本当に面白い。
というわけで、キックオフミーティングの報告?でしたが、劇団静岡県史のこの事業のメンバー募集がいよいよ始まります!
興味を持たれた方は、奮ってご応募くださいね~!

アーツカウンシルしずおかとは
アーツカウンシルしずおかは、すべての県民が、様々な表現活動を通して創造的になることを目指します。
アーツカウンシルしずおかは、そのための方法を開発し、制度を整備してまいります。
特に、まちづくりや観光、国際交流、福祉、教育、産業など社会の様々な分野と、文化芸術との協働を促進し、地域資源の活用や社会課題に対応する創造的な取組を支援することにより、地域社会の創造に寄与してまいります。


というものです。
https://artscouncil-shizuoka.jp/
劇団静岡県史は、単なる演劇公演活動と違って、静岡県の歴史を舞台化するために作品に関わる勉強会を開催しますが、それでも大抵の劇団は劇団内で実施されるだけです。
しかし、その勉強会の内容があまりにも良いものだったりするので、劇団員だけでは勿体ないと感じるようになり、一般公開して地域や関心のある人たちと更に共有し、作品創りに生かします。
中には勉強会に参加して、そのまま演劇に参加する人も現れたりします。
インプットされた歴史を、演劇という形でアウトプットすることにより、更に理解が深まるどころか、当時の人たちのような体験をするのです。
それによって時代を越えた他者を知り、ある意味での多様性の理解が増えますよね。
先人たちは当時、何を感じ、考え、行動していたのか?それによって、今の足元も見えてきます。
未来が見えにくい世の中だからこそ、過去を振り返って、先人たちの知恵を借りる。
それによって、未来への予想や、指針が見えたりしてね。
そんな活動を劇団静岡県史は、創作過程で学べるのですが、今年度取り組む事業は、明治~昭和にかけてのプリマドンナ三浦環さんは世界で活躍していた人。オペラ「蝶々夫人」で蝶々さんを2,000回もの公演で演じていた人です。
因みにこの作品、イタリア語で上演されたそうですが、お話は、日本の長崎なんですね。しかもこの役、ソプラノだというのに、比較的音域は低いのだとか?
アメリカの小説を原作にオペラとして蘇った『蝶々夫人』は、日本人なのに、最初は外人が演じてたんですって。
で、そこで抜擢された、三浦環さん。
幼い頃から、日舞やお琴など、日本文化を学んできていた人ですから、重宝されると思います。
『ラスト・サムライ』で、小雪にタオルを持たせることはありません。
そのような、少々、日本人の私たちが「?」と思ってしまうような環境で生まれたエピソードなど、ちょっと面白そうですよね。
という私は、まだまだ勉強中。この創作と、勉強会を通して、脚本にのせていきます。
今年の第1回目のアーツカウンシルしずおかでは、23団体が参加して、地域密着型で様々な文化芸術活動を行っていきます。
本日のキックオフミーティングでは、単に団体紹介だけでなく、ワークショップも行われ、自分たちの活動の価値について考える時間がありました。
コーディネーター北本チームとしては、かけがわ茶エンナーレ実行委員会さん、熱海未来音楽祭さん、藤枝世代をつなぐ商店街づくり実行員会さん、そして今日は本番で参加出来なかった、特定非営利活動法人日本地域部活動文化部推進本部さん、そして我が劇団がメンバーで、共通事項や問題課題、必要性、今後の展望などを、事業が成功した時のイラストを個々の団体が描いて、ディスカッションしました。
その中の共通事項は、いつもの日常の変化や、揺さぶり、元気や刺激、そして気づく場、年齢を越えた寄合というキーワードが出てきました。
コロナ禍で、人を集めることに障害が出てきましたが、その中を連れ出して何かをやる価値、それによる新しいコミュニティや人との繋がりが生まれ、住んでいる人たちが心豊かになることを目的とする必要がありそう。
私個人は「人に迷惑をかける必要性」が、面白いキーワードだなと思いました。
そして、なんと熱海が東京の竹下通り並みに若者が集まってることを聞き、衝撃を受けたり。やはり他者と出会うと、自分との違いを知り、その中で面白い知識や方法論など知り合えて、良い刺激になりますね。
そういう意味では同じ事業支援仲間として、励まし合ったり、切磋琢磨して、更に地域を盛り上げていけるのは良いですよね。
違う意見が出たり、自分のやっていることと違ったりすると、それで人と距離をつくったり、否定されたと被害妄想を持ってシャットダウンしたりする人もいますが、多様性を認め合うことが大事だというのであれば、それを民主主義として議論し合うのは、とても大事だなと思ったりね。
他者と出会うのは本当に面白い。
というわけで、キックオフミーティングの報告?でしたが、劇団静岡県史のこの事業のメンバー募集がいよいよ始まります!
興味を持たれた方は、奮ってご応募くださいね~!